たとえば、
「間違えてはいけない」「もっと効率よく」「正しさがすべて」――
そんな空気の中で、わたしたちはいつの間にか、
心の揺らぎや、小さな芽吹きを見失ってしまったのかもしれません。
恋は、未完成なもの。
家族は、予定通りに育つものではない。
なのに今の社会は、
失敗も、不安も、寄り道も、
どこか「いけないこと」のように押し流してしまう。
結果ばかりを重視する空気が、
わたしたちの“生きること”そのものを、窮屈にしている気がします。
これは、
「正しくあらねばならない世界」で、
恋や家族を育むことの難しさに、
そっと目を向けるための記事です。
間違えられない空気の中で、人は心を閉ざしていく
表情の消えた街で、わたしは立ち止まる

朝の通勤路、職場の廊下、ふと通り過ぎる人たちの顔に――
怒りも喜びも、悲しみさえも、映っていないことがあります。
無表情なのではなく、「感情が抜けてしまった」ような顔。
職場で挨拶をしても、返ってこない。
すれ違っても、まるで誰もこちらを見ていない。
そんなとき、わたしは思うのです。
――この人は、私を“人”として見ていないのかもしれない、と。
冷たい目でも、敵意でもない。
ただ、存在そのものが“無いもの”のように扱われる感覚。
それは、怒られるよりも、見下されるよりも、
もっと深く、ひんやりと、胸に残る違和感です。
誰もが忙しく、目的だけを見つめて歩いているこの社会で、
人とすれ違っても、心がすれ違うことは少ない。
効率や結果がすべてになれば、
挨拶も、会話も、感情も、必要のないものとして
次第に、削られていってしまうのかもしれません。
でも、わたしはそこに、
ほんの少しでもぬくもりが欲しいと願ってしまうのです。
ただ、目が合って、
「あ」と、声が返ってくるだけで、
それだけで、その日がすこし救われる気がするから。
正しさと効率が支配する世界が、なぜ人を孤立させるのか
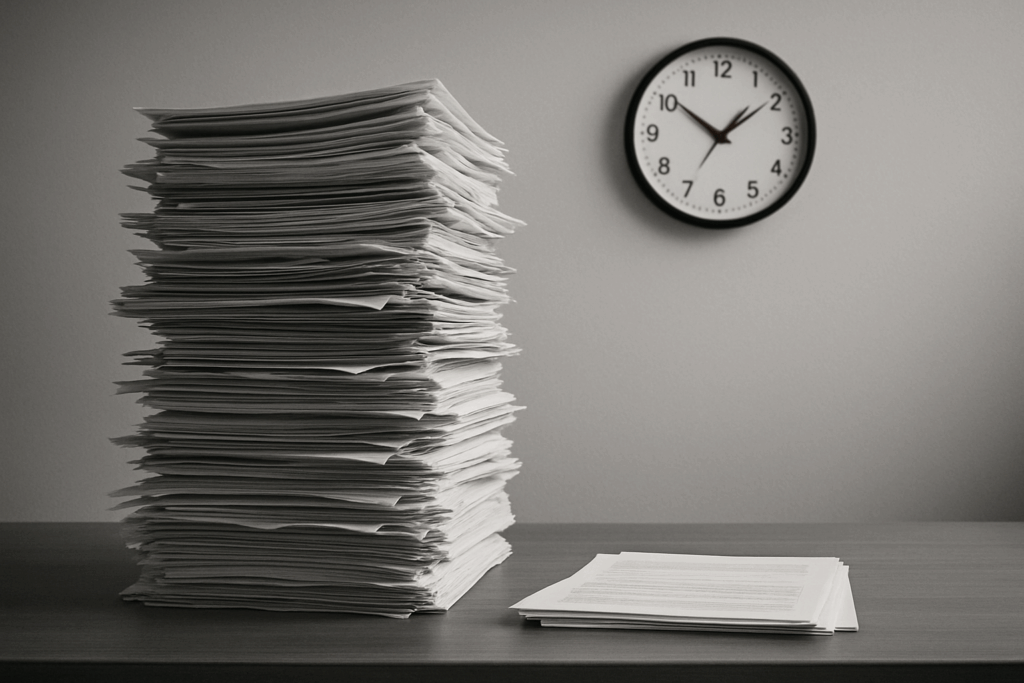
誰かが「間違えた」とき、
その人に寄り添うよりも、
「どうしてそんなこともできないの」と責める空気が先にやってくる。
誰かが「遅れた」とき、
「早くして」と急かす声のほうが、大きく響いてしまう。
社会は、正しさと速さで動いている。
判断は一瞬で、感情は置いてきぼり。
そこに、“人”という存在の揺らぎが入りこむ余地は、ほとんどない。
だから、誰かと違う感性を持っている人ほど、
「わたしはこのままで大丈夫だろうか」と怯える。
そして少しずつ、静かに、孤立していく。
「どうしてそんなことも気にするの?」
「考えすぎじゃない?」
そんな言葉の奥にある、“理解されなさ”の冷たさ。
それでも黙って、
黙って、
自分を責めてしまう人たちが、確かにいる。
正しさの定規では測れない感性。
効率では拾い上げられない声。
そんなものたちが、静かに見捨てられていく社会で、
「生きていてもいい」と思えるには、あまりにも勇気が要る。
人を孤立させるのは、
敵意ではなく、
「何も感じないこと」、
そして「急がされ続けること」なのかもしれません。
正しさ”よりも、“育てあう”あたたかさを

完璧であることが正しい。
間違えないことが偉い。
早く、正確に、結果を出すことが当たり前。
──そんな空気の中では、
心が育つ余白は、どんどん削られていきます。
人は、すぐに「完成」できない。
ゆっくり感じて、迷って、間違えて、
少しずつ、誰かのあたたかさに触れながら育っていく存在です。
それなのに、
間違えた瞬間に否定されたり、
感じすぎることで「弱い」と言われたりしたら、
自分の芽を、自分で摘んでしまいたくもなる。
でもほんとうは、
何が正しいかよりも、
その人のなかで「なにが育っているのか」を、
見守る視点のほうが、ずっと大切なのではないでしょうか。
感性を守るには、正しさよりも、やさしさが必要。
効率よりも、待ってくれる誰かが必要。
ひとりでは信じられなかった「生きやすさ」も、
関係のなかで、すこしずつ信じられるようになっていく。
正しさを押しつけ合う社会から、
おたがいの芽を育てあえる世界へ。
わたしは、そんな場所を、
誰かと一緒に見つけていきたいのです。
未完成なままで、芽吹いていくことを許したい

わたしたちはきっと、
正しくあるよりも、やさしくありたかった。
誰かに追いつくよりも、
自分の足で、自分のリズムで歩いていたかった。
なのに気づけば、
早さや効率に置いていかれそうになって、
「もっと頑張らなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」って、
どこかで呼吸を忘れてしまっていた。
でもほんとうは、
未完成なままで、揺れていていい。
まだ答えが出せない自分も、
まだ誰かとちゃんと向き合えない自分も、
そのまま、ここにいていい。
ひとりひとりの感性が守られる場所で、
それぞれの芽が、静かに芽吹いていくこと。
その時間と空気を、信じていたいのです。



コメント